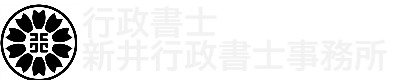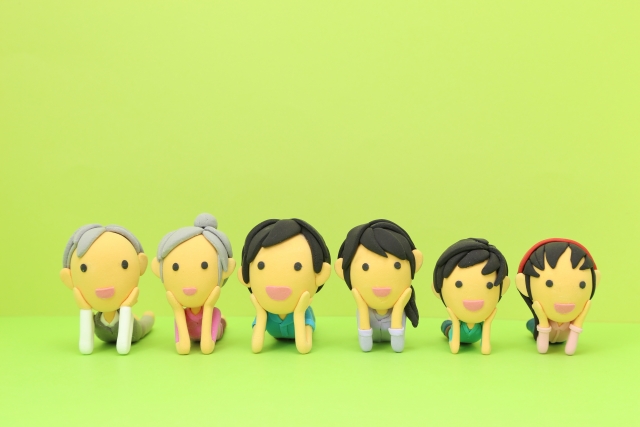遺言作成

🔹 1. 遺言書とは?
・なぜ遺言書が必要なのか?
・遺言書がないとどんな問題が起こる?
📌 「遺言書がないと、相続人同士のトラブルや財産分配の問題が発生しやすくなります。円満な相続を実現するために、事前の準備が大切です。」
🔹 2. 遺言書の種類
| 遺言の方式 | 概要 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 |
本人が全文を手書きして作成。比較的手軽に作成可能。 |
| 公正証書遺言 | 証人2人以上立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝える等、公正証書として要件を満たしたもの公証人が作成し、原本を公証役場で保管。安全性が高く、紛失・改ざんのリスクが少ない。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言の内容は秘密とし、遺言があることだけを教える方法。法務局で保管可能。手続きはやや複雑。 |
遺言書の要件を満たしていない、押印や日付の入れ忘れなどで無効になる恐れがあります。
🔹 3. 📝 遺言書作成の流れ
🔹 STEP 1:遺言書作成の目的を明確にする
✅ 「なぜ遺言書を作るのか?」を整理することが重要!
例:財産の分け方を明確にし、家族の争いを防ぐ
特定の人(配偶者・子・孫・親族以外)に財産を渡したい
事業の承継(経営者が後継者を指定する)
🔹 STEP 2:財産と相続人の確認
✅ 遺言書を作る前に、自分の財産と相続人を整理!
📌 準備するもの
財産の一覧(不動産・預貯金・株式・貴金属など)
相続人の一覧(家族構成を確認し、誰に何を渡すか決める)
🔹 STEP 3:遺言書の種類を決める
✅ 遺言書には3つの種類がある!自分に合う形式を選ぶ!
遺言の種類特徴・ポイント
自筆証書遺言 自分で手書きする方式(手軽だが紛失・無効のリスクあり)
公正証書遺言 公証役場で作成し、公証人が内容を確認(確実 & 安全)
秘密証書遺言 内容を秘密にしたまま作成し、公証役場で保管(手続きが複雑)
💡 おすすめ!
👉「確実に実行される」公正証書遺言が安心!
👉 2020年の法改正により、「自筆証書遺言」も法務局で保管可能!(改ざん防止)
🔹 STEP 4:遺言書の作成
✅ 内容を決めて、実際に作成!
📌 遺言書に書くべきこと
1️⃣ 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
2️⃣ 遺言執行者の指定(遺言の内容を実行する人)
3️⃣ 付言事項(自由記述)(家族へのメッセージなど)
💡 ポイント
👉 遺言執行者(信頼できる人・専門家)を指定しておくと、スムーズに手続きできる!
👉 手書きの場合は、「全文・日付・署名・押印」が必須!(書き方を間違えると無効に!)
🔹 STEP 5:公証役場での手続き(公正証書遺言の場合)
✅ 公正証書遺言を作成する場合、公証役場で手続きを行う!
📌 必要なもの
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
財産の証明書類(登記簿・通帳など)
証人2名(公証人が手配も可能)
💡 ポイント
👉 作成後、公証役場で原本を保管するので安心!
🔹 STEP 6:遺言書の保管と定期的な見直し
✅ 作成後も、定期的に内容をチェック!
📌 見直しが必要なケース
家族構成が変わった(結婚・離婚・子どもの誕生など)
財産状況が変わった(不動産の売却・相続税対策など)
法改正による影響(2024年の相続登記義務化など)
💡 ポイント
👉 「10年に1回」は内容を見直すのがおすすめ!
👉 家族に「どこに保管しているか」を伝えておくとスムーズ!(秘密にしすぎると発見されないリスクあり)
🔹 4. 📌 よくある質問(Q&A)
🔹 遺言書関連のよくある質問
❓ 遺言書を書かずに亡くなったらどうなりますか?
➡ 法律に基づいた相続(法定相続)が適用され、遺産分割協議が必要になります。遺言書がないと、相続人同士のトラブルにつながることもあります。
❓ 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いですか?
➡ 自筆証書遺言は手軽に作成できますが、無効になったり紛失のリスクがあります。公正証書遺言は安全性が高く、確実に実行されます。
❓ 法務局で遺言書を保管できますか?
➡ はい。自筆証書遺言は法務局で保管することができ、紛失・改ざんを防げます。
❓ 遺言書の内容を家族に知られたくないのですが?
➡ 秘密証書遺言を作成することで、内容を家族に知られずに保管できます
❓ 遺言書の内容は変更できますか?
➡ 「はい。新しい遺言書を作成すると、古いものは無効になります。」
🔹 5. 報酬表
| サービス内容 | 料金(目安) |
|---|---|
| 公正証書遺言の作成サポート(遺言書原案作成+公証役場手続きサポート) | 50,000円~ |
| 自筆証書遺言の作成サポート(遺言書の作成支援+法的チェック) | 30,000円~ |
📌 公正証書遺言の場合、別途「公証人手数料」が必要になります。
📌 その他の費用について
✅ 公証役場の手数料、印紙代、郵送料などの実費は別途かかります。
✅ 証人2名の立会いが必要な場合は、別途料金(10,000円~/人)
✅ 追加対応が必要な場合は、事前にお見積りをお出しします。
🔹 6. 📌 まずは無料相談!
💡 「どんな遺言書がいいの?」「相続トラブルを防ぐには?」
そんな方のために 無料相談を実施中!
📌 【無料相談の内容】
✅ 遺言書の種類と違い(公正証書・自筆証書・秘密証書)
✅ 最適な遺言書の選び方
✅ 費用の概算お見積り
お問い合わせフォーム
- 氏名必須
- メールアドレス必須
- お問い合わせ内容必須